詩を書こう④:知っておきたい詩のテクニック


詩に多く用いられる技法を5 つ挙げる。技巧を凝らせば詩になるということではないが、覚えておけばいざというときに出てくる!
オノマトペ:音にどんな言葉を与えるか
擬音語は一語で情感がストレートに伝わっていいが、鉄砲は「バーン」のように紋切り的に使うと陳腐になり、どう書くかを何も考えていない詩に思えてしまう。
川上弘美に、草むらでおしっこをした音を「さやさや」と書いた小説があるが、どう聞こえるかを主観でとらえ、主観でありながら感じがありありとわかるという使い方をすると、擬音語は絶大な効果を発揮する。

比喩:外から似たものを探してくるのが比喩
「何を思い浮かべてもいいですが、赤いバラだけは思い浮かべないでください」という実験がある。
そう言われても、「赤いバラ」と言われた瞬間、すでに頭に浮かんでいる。
比喩も同じ。たとえられたものは本来借りもので、下の詩で言えば「私」は「荒れ狂ふ海」ではないし、「私の耳」も「貝のから」ではないが、たとえられた言葉が居座り、読む人の頭の中に残る。
私は夜ごとを荒れ狂ふ海だ。
古い罪に新らしい罪をかさねて、
いけにへに重たい歎きの海だ。
(ヘッセ「私は星だ」部分、「ヘッセ詩集」より)
耳
私の耳は貝のから
海の響をなつかしむ
(ジャン・コクトー「耳」、堀口大學訳詩集「月下の一群」より)
たとえられるものは、たとえるものに似ていないと比喩にならないが、似すぎていても効果がない。また、たとえるものの特性や状態が具体化すると効果的。
下の詩は、皿の上に何かあるように想像してしまう。比喩とは違うが、比喩と似た効果がある。
直喩
直喩は「のような」「のごとし」がつく比喩。英語ではシミリーと言い、これは「同じように」「似たもの」という意味がある。「私の耳は貝のからのようだ」が直喩。
隠喩
隠喩は「のような」「のごとし」を省略した比喩。英語で言うとメタファー。「私の耳は貝のから」と言いきることで、たとえた感じがなくなり、主観的で強い表現になる。
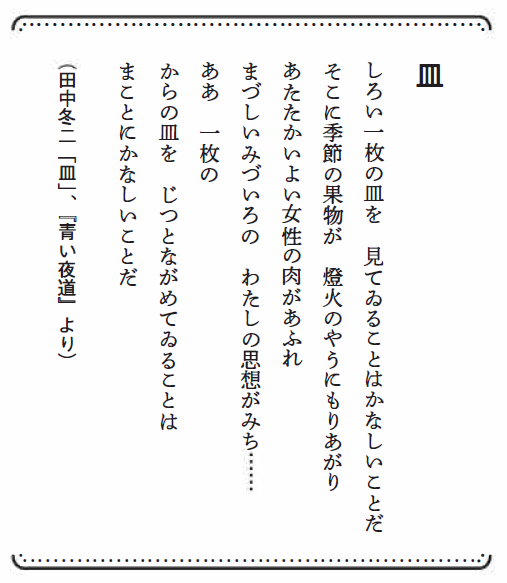
押韻:韻を踏むと音楽的心地よさが出る
押韻とは、いわゆる「韻を踏む」という技法。頭をそろえる頭韻と、語尾をそろえる脚韻がある。
韻は2 つ以上が対のようになったもので、そうすると音楽的に心地いいリズムを刻む。
左記の詩では、第1連の1行目「遠い」と2行目「扉」は卜音の頭韻。3行目「乱れて」と4行目「緑の」はミ音の頭韻。
1行目「なか」と3行目「はだか」はカ音の脚韻、2行目「待ち」と4行目「娘たち」はチ音の脚韻。
計算された音の響きが、この詩を音楽的にしている。ただし、韻だけにとらわれると内容が空疎になるので注意。
頭韻
1 行目と2行目の頭を同じ音、または同じ段(あ、か、さ、た、な……) の音にしたり、「扉のひらく時を待ち」のように「と……と……」とするなど頭で韻を踏むこと。
脚韻
語尾で韻を踏むこと。下記の詩の第2連で言うと、「畔りには」の「には」と「燃える岩」の「いわ」、「立昇る」の「ぼる」と「透きとほる」の「ほる」が脚韻となっている。
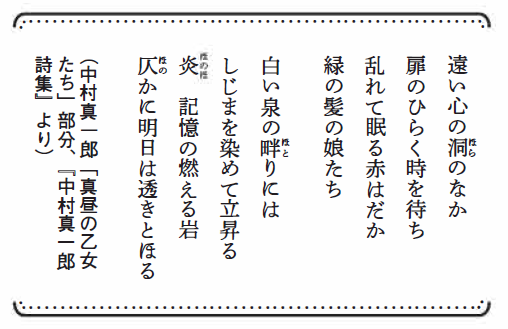
倒叙法:語順を変えて強調
平叙文であれば「賢こさうな泣きつらを見たか。背嚢がたの汗を見たか。からだ中から革具の匂いのしてたあの若い兵隊を見たか」となる。
語順としてはごく普通の文章だから、何も引っかからずすっと読み流される可能性もあるが、「見たか」のようにいきなり動詞から始まっているので記憶に残り、同時に「何を?」と思う。
変化があるので強調ができ、躍動感も出せる技法。
見たか
賢こさうな泣きつらを
背嚢がたの汗を
からだ中から革具の匂いのしてたあの若い兵隊を
気づいたかあいつがちらりと見たのを
君に何か言ひかけようとしたのを言ひかけようとして言ひかけ了せなかったのを
奴は言はうとしたのだ
——見てくれおれをおれは兵隊だ
おれは兵卒だ
そしておれが兵卒だといふことが一切なのだ
でかい兵器廠がグワングワン吠え立て
おれ達は年がら年中人ごろしの稽古だ
(中野重治「兵隊について」部分、「中野重治詩集J より)
リフレイン:繰り返して強調する技法
下の詩では、各連の最後で「日も暮れよ鐘も鳴れ/月日は流れわたしは残る」がくり返されます。この反復をリフレインと言う。
これはわかりやすい形だが、違う連の同じ箇所に同じ言葉をもってくるといった細かいリフレインもあり、これは押韻に似た技法。
強調したいフレーズをくり返せば、そこが印象に残る。

※本記事は「公募ガイド2018年7月号」の記事を再掲載したものです。