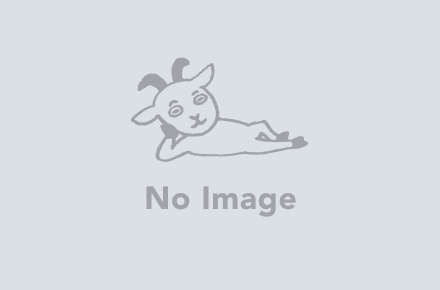本や読書が好きなら「書評」を読もう、書いちゃおう!(2/2)


書評を書く5つのポイント
「自分でも書評を書こう」と思ったら、まずは一旦、なにかしらの書評を読んでみましょう。(本記事の最後に、書評を読めるWEBサイトもご紹介します)
また、実際に書評を書くときには、以下のポイントを押さえるとうまくいきます。
1)その本を手にしたことのない人でもわかるように書く。
自分がなぜそう感じたか、なぜ評価するか、ということを論理的に示すためには、最低限の本の概要をあらかじめ示す必要があります。他の書評を読んでコツを掴みましょう!
2)作者の他の作品との比較や、刊行された時代背景(災害や社会的な出来事など)について考えてみる。
作品そのものから得られた情報だけでなく、作者のプロフィールや刊行年にも注目してみましょう。たとえば、戦争やコロナ禍、景気や流行の影響が表れている可能性もあります。
3)その本の魅力的な点だけでなく、批判的な点も書いてよい。ただし、かならず客観的で論理的な理由を書く。好き嫌いという感情だけで書かない。
必ずしもその本を褒めちぎる必要はありません。批判も評価のひとつです。ただし、感想のように好き嫌いだけで語らず、どの部分が気になったのか、なぜ批判するべきだと考えるのか、理由を述べましょう。
4)ポイントを絞って深く書く。
読みやすい書評(自分にとって振り返りやすい書評)は、論点を絞って書かれています。もっとも書きたいポイントに絞って深く書きましょう!
5)「本の概要→今回の書評で取り上げるポイント→そのポイントを取り上げ、評価する理由→まとめ」という流れがおすすめ。
レポートの書き方と似ていますが、基本的な流れを押さえると書きやすく・読みやすい書評になります。何から書いたらいいのか迷うときには、ぜひ思い出してください。
書評を発表しよう!
読書記録として自分の手元に残しておくだけでもいいですが、たとえば書評ブログを開設してはいかがでしょうか? 自分の記録にもなる上、多くの人に読んでもらえそうです。
ブログ執筆サイト「note」は誰でも簡単にブログを開設することができ、また「書評」「読書・書評」などの検索用タグをつけることが可能です。多くの人が書評を書いているので、書評を書きたい人・読みたい人が自然と集まってきます。
また、プロの書評が読める「bookbang」も執筆の参考になりそうです。
書く自信がついたら、公募に挑戦するものいいかもしれません。たとえば大学生の方は、多くの大学図書館で書評コンテストを実施しています。短歌関連書限定になりますが、以下のBR(ブックレビュー)賞にも毎年優れた書評が集まります。
なお、Kouboで「あなたとよむ短歌」連載中の、歌人・柴田葵さんも書評を書くのが好きだとか。たとえば週刊文春の書評欄に掲載の記事
「じゃんけんで負けて蛍に生まれたの」などの句で知られる俳人が気づいた “老い”にまつわる「残酷な事実」
は、歌人として、あえて俳人の本について書評を書いてほしいという依頼で書いたものだそうです。
自分の経験を生かして、その本の魅力を語る書評。その奥深く楽しい世界を、あなたも探究してみませんか?