【第2回】 ヤマモトショウ 創作はいつまで続くのか 「はじめてのオリジナル曲」


2015年の解散後はソングライターとしてでんぱ組.inc、私立恵比寿中学、ばってん少女隊、きゅるりんってしてみて ら多数のアーティストに詞や曲を提供している。
FRUITS ZIPPERに書き下ろした楽曲「わたしの一番かわいいところ」はTikTokで30億回再生を記録し、MUSIC AWARDS JAPANの最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞。
2024年2月にはミステリー小説『そしてレコードはまわる』、2025年8月にはエッセー集『歌う言葉 考える音 世界で一番かわいい哲学的音楽論』を上梓。

今を時めくソングライター、ヤマモトショウさんによる新連載。
マクドナルドの月見商品のWEBコマーシャルでは、「いまだけ月見食べ美」の楽曲「今度いつきみに会えるのかな」の作詞・作曲・編曲など、前回の記事公開からの1カ月でも大活躍されています。そんなヤマモトショウさんの、創作の原点は? どんなきもちで創作をしているの? どこよりも深く語ります!(編集部)
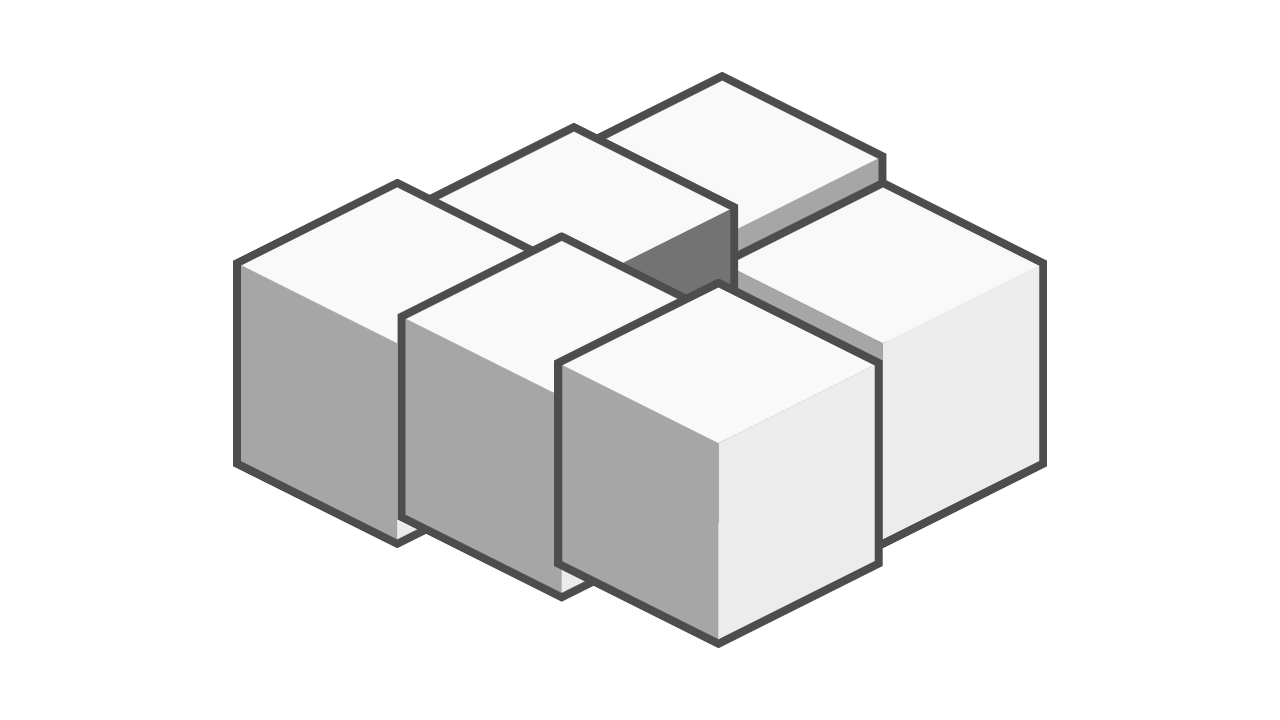 第2回 はじめてのオリジナル曲
第2回 はじめてのオリジナル曲段階αのはじまり
私の創作は、中学生から高校生にかけて段階αとしてスタートした。これは、実際には具体的に何かをつくっているわけではないのだが、コピーバンドをはじめたこと、そしてそのバンドをもって人前に立って少なからず賞賛を受けているという状態のことである。
これは何らかの錯覚なのだが、それでもその錯覚は人を勘違いさせるのに十分なのである。
私は、さすがにその時に音楽のプロを目指そうなどということを思いはしなかったが、それでも少し「音楽ができる自分」というものを自認するようになった。学校を見渡しても、ギターが弾ける人というのは数人しかいないのだから、これは確固たる特技だろう、とも思ったものだ。
前回も書いた通り、実際にはこの段階で弾けていたギターの技量というのは、「やっているかやっていないか」くらいの差しかないので、単にギターを買ってもらうことができて、練習する時間が少しあったということに過ぎないのだが、それでも往々にして多くのことは勘違いから始まっているのだから、こうしてつらつらと言い訳がましく書いていることでなんとなく、今振り返っているこの感情を察していただけたらとは思う。
初のオリジナル曲。創作への姿勢はどう変わる?
さて、高校生時代に少しだけ、この初期段階から先に進むきっかけが到来した。というのも、私の母校では毎年生徒有志によって文化祭のテーマソングが作られるのだが、高校三年生のときには私のやっていたバンドがそれを担当することになったのだ。(基本的には校内から選ばれるということだったが、継続的にバンド活動をしていたのが私のバンドくらいだったので、ほとんど自動的に決まっていたように思う)。
私にとって、明確な「オリジナル曲」というものができたのはこの時がはじめてだったように思う。文化祭ではもちろんこの曲を演奏する機会があったし、文化祭までの一ヶ月間くらい校内放送で流れ続けていたので、たぶんその後を考えても自分周辺での浸透度という意味ではトップクラスになった楽曲だろう。

ところで、この楽曲においては私は「作詞作曲」などはしていない。私が作詞作曲を、少なくとも外に開かれたものとして行うようになるのはまだ数年先のことである。(自宅でちょっとつくるくらいはやっていた)
作詞作曲はしていないにしても、バンドとしての初のオリジナル曲が高校三年生の時というのは、今活躍している音楽のプロたちと比べたら相当「遅い」のではないかと思う。
もちろん当時と今では、テクニカルな状況がかなり違う。今は、自宅で音楽制作を完結できるような環境(DAWとかDTMといったもの)が、かなり安価で手に入る。昔だったら、お金をためてギターなど楽器を買っていたその資金で、今はDAWソフトを手に入れて、音楽制作を始めることができるだろう。そしてそれをインターネットを通じて発信することもかなり容易になった。
私が高校生の頃にこれがあったとして、それをやったかはわからないが、少なくとも当時の環境で今くらいの音楽制作をするにはプロとしての環境や資金がなければ難しかっただろう。だからこそ、当時はライブハウス、あるいは路上ライブのようなところで、その「才能」をアピール必要があったわけだ。そして、その才能に対してレコード会社や芸能マネジメントなどが、投資という形で音楽を制作するのがスタンダードなスタイルだった。(DAWが音楽制作、クリエイティブの世界にどれだけインパクトを与えたのか、ということについてはこの連載の非常にクリティカルな部分にも直結するので、いずれ書こうと思う)
いずれにしても、高校三年生当時の自分はそのスタート地点にもたっていなかったといえるだろう。ようやく、オリジナル曲をひとつ作ったわけだ(といっても、自分が作詞作曲したわけではないが)。
しかし実は私はここで、ひとつ大きな回り道をすることになる。というのも、このオリジナル曲というのが、やはり学校の中、文化祭といった特殊な環境のために、「それなりに評価」されてしまうことになるのだ。