【第3回】 ヤマモトショウ 創作はいつまで続くのか 「高3で作った映画とレガシー」


2015年の解散後はソングライターとしてでんぱ組.inc、私立恵比寿中学、ばってん少女隊、きゅるりんってしてみて ら多数のアーティストに詞や曲を提供している。
FRUITS ZIPPERに書き下ろした楽曲「わたしの一番かわいいところ」はTikTokで30億回再生を記録し、MUSIC AWARDS JAPANの最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞。
2024年2月にはミステリー小説『そしてレコードはまわる』、2025年8月にはエッセー集『歌う言葉 考える音 世界で一番かわいい哲学的音楽論』を上梓。

「日本版グラミー賞」ことMUSIC AWARDS JAPANや日本レコード大賞を受賞した、FRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」を始め、数々のかわいいヒット曲を生み出している、いま大注目のソングライター、ヤマモトショウさん。
今月も、松田聖子オフィシャルトリビュートアルバム「永遠の青春、あなたが そこにいたから。 〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜」では FRUITS ZIPPERが歌う「青い珊瑚礁」のアレンジを手掛けるなど大活躍。そんな令和のヒットメーカーの創作に対する姿勢の変遷をご覧ください。 (編集部)
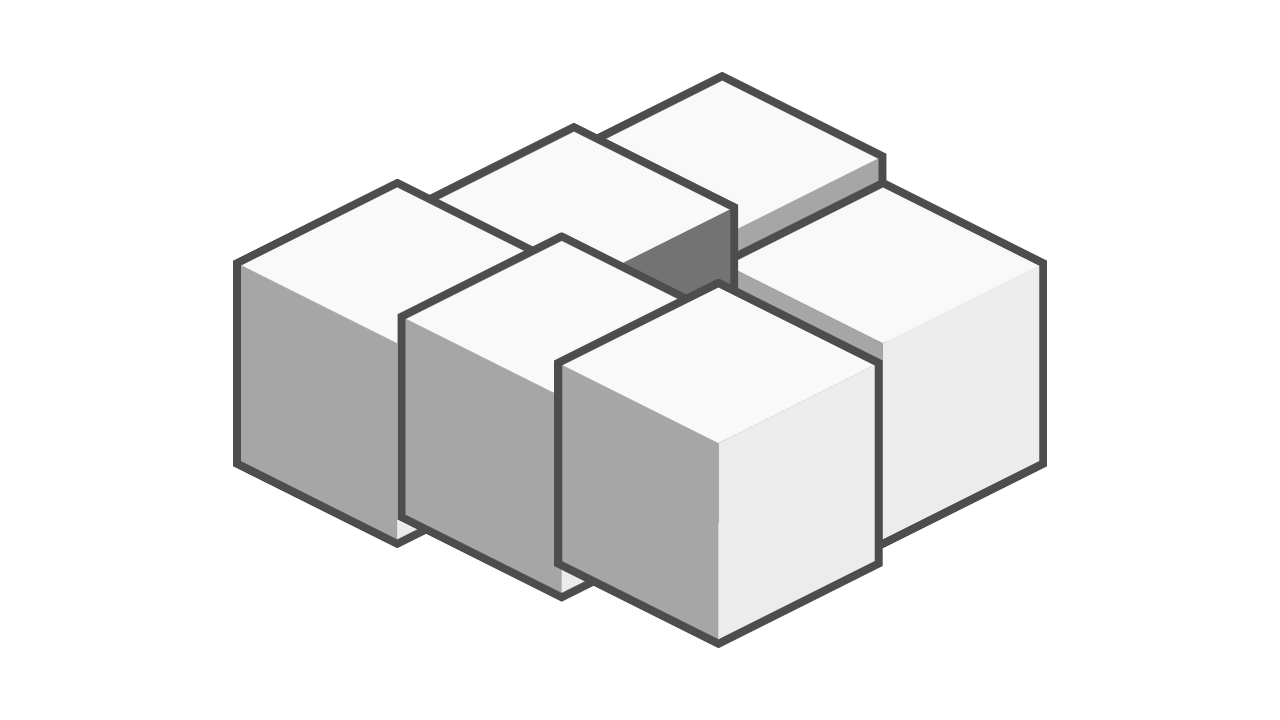 第3回 高3で作った映画とレガシー
第3回 高3で作った映画とレガシー高校生、映画を撮る
自身の創作の歴史を振り返る旅は、今回もまだ高校時代を抜け出すことができないかもしれない。前回書いたように高校三年生の私はオリジナル曲をつくりはじめたものの、それはまだ創作の初期段階、つまり段階αから抜け出すようなものではなかったのだが、実は高校生の頃にもう一つ創作的行為が行われていた。
これも文化祭での出来事なのだが、私の母校では高校三年生のクラスが文化祭で何かしらの出し物をしなければいけないというルールがあった。私たちのクラスはそこで映画をつくったのである。
私がここでいいたいのは「映画をつくる」ということそのものが創作的だ、ということではない。
このクラスごとの出し物は、受験も控えた三年生ではあるものの、ある意味では一年で一番盛り上がり、楽しめるイベントである。しかしそうはいっても時間のなさから、どうしてもその内容はちょっとしたミニゲームのようなものをつくるとか、出店を出して終わるというようなものになってしまう。
私の通っていた高校はその地域では一番の進学校の一つとされていたが、まがいなりにも「賢い」とされている10代後半の若者の自己表現がこれか、とがっかりしたのが高校一年生のときで、どうにか三年生になったら別のことがやってみたいと思っていたのだ。私のいたクラスは学年で唯一三年間クラス替えがないことがわかっていたので、二年生の頃から友人たちと準備をして、30分ほどの短編映画の上映をすることになった。
映画の成功と、思わぬ影響
この作品が「映画」として、優れていたのかどうか、それは正直わからない。内容は有名作のパロディだし、役者は自分をはじめ素人以下、編集は当時にしては頑張っていたとは思うが今から考えればお粗末なものだろう。どちらにしても、私たちにとって大事だったのは、これまでの常識を覆して「映画をつくった」という事実なのだ。(ちなみに、この文化祭では毎年ナンバーワンの出し物を決める投票があるのだが、もちろん受賞した。というよりも、従来の比較の指標の外側にあるものが現れたらもはや投票の意味もなかっただろう)。
その後少なくとも、十年くらいそのクラスでは代々映画がつくられることになったようなので、これはある種のレガシーになったということだと思う。(そうなってしまうとつまらない、というのもいうまでもないことだが)私たちは映画をつくったと同時に、「流れ」をつくったのである。これはオリジナル楽曲をつくったということよりも、ある意味ではクリエティブだったのではないかと思っている。
実際私は、自分のつくったもの、やったことが後の世代に影響を与えているというその事実が、実は作品をつくり残していくということの本質的な帰結の一つなのではないかと考えている。それは自分がつくるものが、少なからずこれまで世に生まれた多くの素晴らしい作品からの影響を受けているからである。このように創作を定義することの是非については、今後何度も議論することにはなると思われるが、少なくともこの時の短編映画が何かしら後続に影響を与えたことは間違いない。