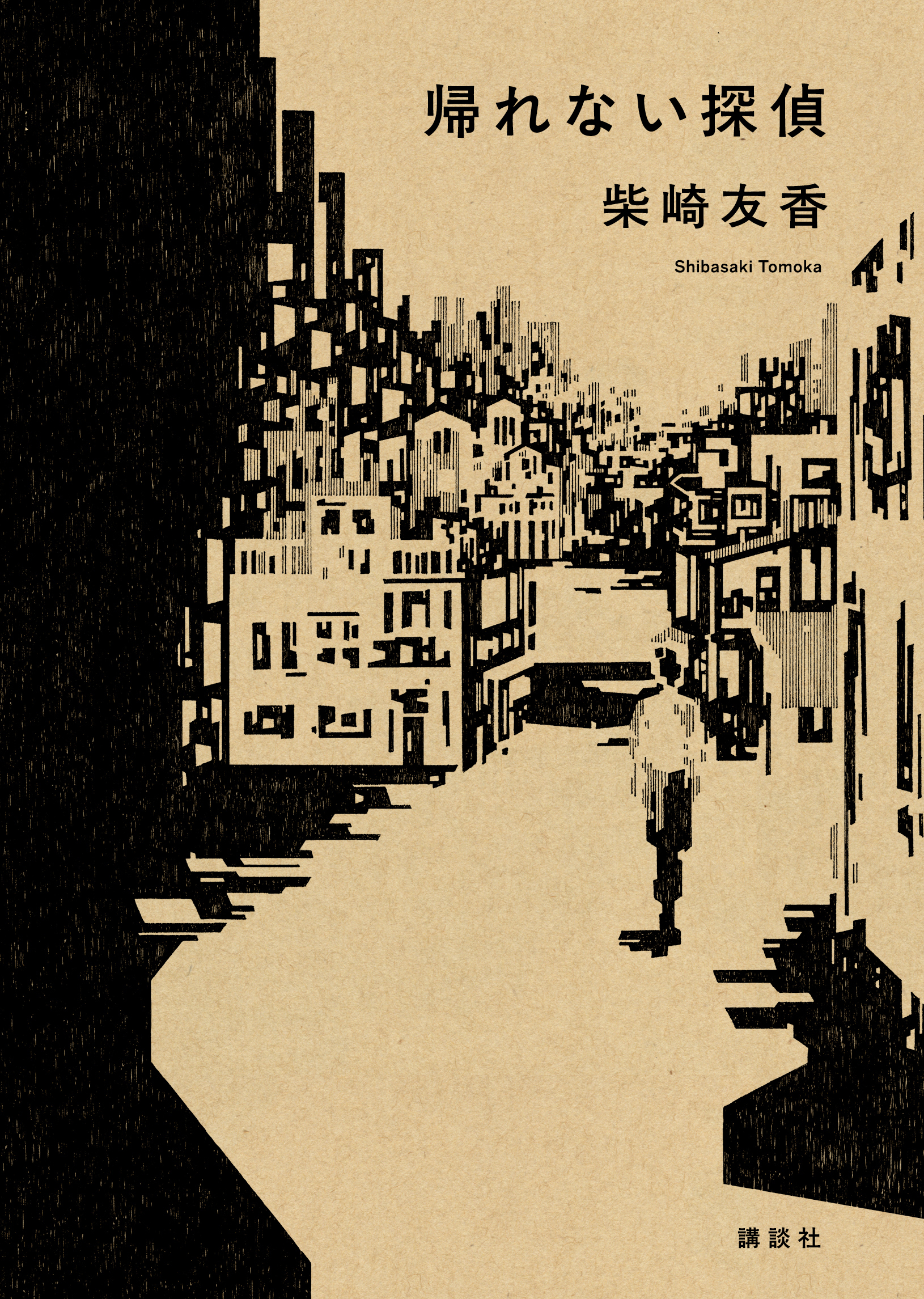第14回のゲスト選考委員は、芥川賞作家の柴崎友香さん。
デビューしたきっかけから書き続けるための秘訣まで、
創作者が知りたいあれこれを伺いました。
季刊公募ガイドの巻頭インタビューの別バージョンです!
純文学と探偵小説は、
そう遠くはないと思った
―― 新刊の『帰れない探偵』は探偵小説ですが、探偵という設定にされたきっかけはなんでしょうか。
柴田元幸さんが編集長をしている「MONKEY」で探偵特集があり、そのときに短編を書いてもらえませんかと依頼があったのがきっかけです。
私自身も「私に探偵小説? なんで?」という感じで、どうしようかと思ったのですが、考えてみれば、私が現代アメリカ文学を読み始めたきっかけは、柴田元幸さんが翻訳されたポール・オースターの『鍵のかかった部屋』というニューヨーク三部作の一つでした。大学生のときにこの小説を読んで興味を持ち、オースターや他のアメリカの作家の小説を読んでいきました。
―― そういう探偵小説もありだと思った?
『鍵のかかった部屋』を含むニューヨーク三部作は探偵小説の形を取りながら、哲学的な問いを追っていく作品です。私がこれまで書いてきた小説は、地図や写真から人の記憶や過去を探り、想像していく作品なので、そう遠くはないんじゃないかということで書いてみました。
実際、書いてみたら、探偵は全然関係ない人の話を根掘り葉掘り聞けるから、これは面白い形式だなと。それでその後、「群像」で連作短編として続きを書くことにしました。
自分自身では探偵という設定は思いつかなかったと思います。依頼をいただいたことで、いいきっかけになりました。
―― 確かに探偵小説は謎を追い、純文学は人間の真実を追求するということで、共通する部分が多いですね。
私はジャンルで分けて考えることはあまりないのですが、探偵小説は、その枠組みを使って幅広い作家が様々なチャレンジができるからこそ、書き続けられているんだと思います。
―― 『帰れない探偵』も哲学的で、存在ってなんだろうと問うようなところがあります。
自分がこの何年か、ほかの作品でもずっと書いてきたテーマとつながっています。時間とか場所とか、人の記憶とか、ふだん接することがない人のことも人間は想像できるということではないですかね。
―― 探偵と純文学の融合ということでは、安部公房の『燃え尽きた地図』を思い出します。
『燃え尽きた地図』の映画版がまた面白くて、勝新太郎、市原悦子、渥美清という個性の強いキャストで……。探偵といっても斬新な試みの小説が多く書かれていて、探偵小説と言われたとき、思い浮かんだ作品の一つが『燃え尽きた地図』でした。
―― 『帰れない探偵』の設定は「今から十年くらいあとの話」ですが、近未来にしたのはなぜでしょうか。
今となってはよく覚えていないのですが、この五年ぐらいの間に並行して書いていた『続きと始まり』や『遠くまで歩く』は、十年前から見れば現在は十年後だし、十年後の人から見れば現在は十年前なんだということを書いていて、過去の蓄積や人の記憶について考え続けていたので「十年くらいあとの話」という設定になったんじゃないでしょうか。
―― 主人公の探偵が所属している団体が「世界探偵委員会連盟」です。「世界探偵委員会」でもなく、「世界探偵連盟」でもなく、「世界探偵委員会連盟」というのが面白いです。
リアリティーのある自然な名前ではなく、いかにも作ったような不自然な名前にして、架空の街をさまよう不安定な感じを出しました。
―― 世界探偵委員会連盟には本科と専修コースがあり、専修コースを卒業すると二つ星にランク付けされるとか、妙に現実的です。
フィリップ・マーロウやシャーロック・ホームズなど、孤独でアウトロー、あるいは、天才的な推理力がある探偵が人気ですが、「では、どうやって探偵になるんだろう」と考えたときに、私が現在の世界でイメージしたのは職業としての探偵でした。だから、今のいろんな職業がそうなっているように、学校を出て資格を取ってという設定にしました。
―― 「探偵は依頼者の事情に深入りしない」「探偵はお互いの個人的なことについて質問してはならない」など、リアルで具体的なことも出てきます。これは調べて書かれたことでしょうか。
これまで読んできた探偵小説や観てきたドラマから、こういうの、ありそうというものを書きました。探偵はフィクション性の強いキャラクターなので、探偵とは?と想像を広げていった感じですね。
読んでいる間は、小説の中の世界を
生きることができる
―― 『帰れない探偵』は純文学作品であり、探偵の依頼があってもエンタメ的に展開するわけではありません。なのに、非常に面白く読めます。となると、小説の面白さとはなんでしょうか。
少し前に、理系の大学で教えている方と対談しました。学生はそんなに小説を読んでいなかったり、小説の面白さがいまひとつわからないという人が多い。それで学生に小説の面白さを伝えるために、「小説は他人シミュレーターだ」と説明したそうです。
つまり、「別の人間として世界を体験してみることができる。それが小説なんだ」と言ったら、学生たちが「そう言ってくれればわかる。早くそれを言ってくださいよ」となったそうです。
ふだんは自分としてしか体験できませんが、それが小説となると語り手や登場人物の身体や思考を通じて、読んでいる間は小説の中の世界を生きることができます。ふだんの生活だったら感じられないことや、自分だったらこういうことはしないと思うことも、小説を読んでいる間は身近なものとして感じられるかもしれません。
―― 自分ではない誰かになれる?
ごく普通の日常が書かれていても、別の人の感覚を通じて書かれていると、面白いと感じます。ふだん見ていたり、こうだろうと思っているものとは違うものとして感じられるからです。自分が知っている世界を体験し直すことができるということです。
―― 体験し直すというのが面白いですね。
体験し直すのも小説によっていろんなやり方があります。こういうのもあったのかとか、今まで見えていたものとは違うものに見えたりとか。たとえば、友達がなぜあんなことを言うのかわからなかったことも、小説として読んでみると、ちょっと想像できるかもしれないと思ったり。そういうふうにちょっとだけ見え方や感じ方が変わる、違う世界を体験できるというところが小説の面白いところなんじゃないかなと思います。
―― 疑似体験させるにはリアルに書かないと世界に入り込めないところがありますが、本当の話かなと思わせるにはどうしたらいいと思いますか。
リアルじゃない設定でもいいですが、小説を読んでいる間はその世界の中にいる感じがするように書けたらいいです。登場人物のちょっと横で見ているぐらいの距離感で書けたらいいなと思っています。
骨組みというか、こういうふうにして作っていますというのが先に立ってしまうと、ちょっと引っかかってしまい、小説を読んでいるはずなのに違うことが気になってしまうかもしれないですね。
テイストや雰囲気に
合った文体がある
―― 小説には説明と描写があり、よく「説明をするな」と言います。
説明も小説の中で語りとしてうまく説明できているといいんですが、映画を観ていたら隣から「あの人のプロフィールは」と説明されているみたいな感じというか、「ここはこうです」と横から急に解説されているみたいな感じになってしまうと内容に集中しにくいですよね。
―― ここは描写がいい、ここは説明したほうがいいという線引きはできますか。
人物や場所などは説明しないといけない部分もありますが、書きすぎると、それこそ設計図を見せられているような感じになってしまう。あくまでも小説の中の声として書くのがいいと思います。
―― 描写の練習法はありますか。
私はデビューして2作目か3作目ぐらいのときに、担当の編集者さんに「柴崎さんは、会話はすごくいいんだけど、描写をもうちょっと頑張ろうね」と言われて、描写か、難しいなと思った記憶があります。
―― どうされましたか。
その場の感じがすごくよく伝わってくる、うまいなと思う作家の小説を読んだり書き写したりしました。小説はまず、たくさん読む、繰り返し読むことがなによりです。
―― よく文体と言いますが、文体ってなんですかね。
その作家の個性としての文体という意味もあると思いますが、私はその小説にふさわしい文体というもののほうが大事かなと思います。その小説にとって一番合っている文体を探すということをいつも考えています。
―― 具体的には?
『帰れない探偵』で言えば、「世界探偵委員会連盟」のようなディテールの架空度を調整したり、「これは十年くらいあとの話」という語りにしたり、パラレルワールドや近未来みたいな設定にすることで誰がどこから語っているのか、視点を決めていきます。
一人称で語ったほうが合っているか、三人称の語りで書いていったほうがいいかということもあります。その小説の持つテイストや雰囲気は文体によって大きく印象が変わります。
―― 文体が合っているというのは?
英文学で文体のことをボイスと言いますが、そのストーリーを語るときに合っている声があると思うんですね。怖い話やシリアスな話をするのに、賑やで楽しそうな感じで話すと、それはちょっと合っていないとなりますよね。
―― 台なしになってしまいます。
映像作品でのナレーションを入れるとしたら、合っている声を探すと思うんですよ。低くて安定感のある声の人がいいなとか、繊細で柔らかい感じの声の人が合っているなとか、それに近いのかなと思います。意外性のある声や語り方で、それまでにない作品を作る方法もあるでしょう。
―― なるほど、よくわかりました。
何行か読んだだけで、あの作家だとわかる文体もありますし、作品ごとの文体もありますが、私は毎回どういう書き方をしたら自分がこの小説で実現したいと思っていることに一番合った文体かなと考えます。そこは毎回試行錯誤ですね。
―― 創作している方にとても参考になったと思います。ありがとうございます。
応募要項
課 題
■第14回 [ 卒業 ]
わたくし、「卒業」という言葉が好きなんです。「入学」よりずっと。なんだか晴れがましいような、寂しいような、恥ずかしいような、未来があるような、過去が思いだされるうような。そんな言葉ですよね。(高橋源一郎)
締 切
■第14回 [ 卒業 ]
2025/8/9(23:59)
応募規定
400字詰原稿用紙の換算枚数本文5枚厳守(数行の増減は可)。
データ原稿はA4判40字×30行、縦書きの設定を推奨します。
(テキストデータは横書きでかまいません)
枚数が規定どおりか調べたいなら便宜的に20字×20行の設定にし、最終ページを見れば5枚ちょうどかどうかがわかります。
応募方法
WEB応募に限ります。
応募専用ページにアクセスし、データ原稿のファイルを添付。
(ファイル名は「第○回_作品名_作者名」とし、ファイル名に左記以外の記号類は使用不可)
作品の1行目にタイトル、2行目に氏名(ペンネームを使うときはペンネーム)、3行目を空けて4行目から本文をお書きください。
本文以外の字数は規定枚数(字数)にカウントしません。
作品にはノンブル(ページ数)をふってください。
応募点数3編以内。作品の返却は不可。
Wordで書かれる方は、40字×30行を推奨します。
ご自分で設定してもかまいませんが、こちらからもフォーマットがダウンロードできます。
※第14回より郵送での応募は受け付けがなくなりました。
応募条件
作品は未発表オリジナル作品に限ります。
入賞作品の著作権は公募ガイド社に帰属します。
AIを使用して書いた作品はご遠慮ください。
入選作品は趣旨を変えない範囲で加筆修正することがあります。
応募者には公募ガイド社から公募やイベントに関する情報をお知らせすることがあります。
発 表
第14回・2025/10/9、季刊公募ガイド秋号誌上
賞
最優秀賞1編=Amazonギフト券1万円分
佳作7編=記念品
選外佳作=WEB掲載
※最優秀賞が複数あった場合は按分とします。
※発表月の翌月初旬頃に記念品を発送いたします。
配送の遅れ等により時期が前後する場合がございます。
お問い合わせ先
ten@koubo.co.jp
応募作品添削サービス!
「小説でもどうぞ」の応募作品を添削します。
受講料 5,500円
https://school.koubo.co.jp/news/information/entry-8069/