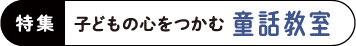#03 基本が大事 童話のつくり方
- タグ


イラスト:seesaw.
童話を書くなら、童話に顕著な物語の型と、物語世界に没頭する子どもという存在について知っておきたい。童話と子どもに関する基礎知識を学ぼう。
01子どもが読みたくなる設定
子どもに読ませたい童話ではなく、子ども自身が自ら手に取りたくなるような設定とは? 童話とは何か、子どもとは何かというところから考えてみよう。
童話と子どもに関する大前提
童話を書くなら、童話がどういうもので、子どもがどういう存在か確認しておこう。前提が間違っていたらゴールには行きつかない!
【童話とは】
子どものためのお話。主として6歳~12歳ぐらいの小学生の読み物。童話公募の場合、特に指定がなければ幼児から小学校3年生くらいの子どもを対象にすれば間違いない。昔話、寓話、道徳的な訓話とは一線を画す。
【子どもとはどういう存在か】
子どもは社会性を身につけている過程にあり、多かれ少なかれ、「一人前の大人になれ」「親のごとくあれ」という抑圧を受けている。教育やしつけそのものは正しくとも、本能的欲求と社会性との間で葛藤している。読書などで抑圧から解放されると、大人以上に大きなカタルシスを得るのはそのため。
童話のストーリーの型
童話には「行って帰ってくる」という型をとるものが多い。同じ場所に帰ってくるが、何かが変わっている。童話(物語)特有のこの型を学ぼう。
【童話に多いパターン】
「はないちもんめ」に代表されるように、子どもの遊びには「行って帰ってくる」ことをくり返すものが多い。絵本『アンガスとあひる』を訳した瀬田貞二は、このことから、
〈とにかく何かする、友だちの所へ行ったり冒険したりする。そしてまた帰ってくる。(子どもが)そういう仕組みの話を好むのは、当然じゃないでしょうか。〉(『幼い子の文学』)
と言っている。言われてみれば、「桃太郎」や「浦島太郎」など昔話にも「行って帰ってくる」構造の話が多く、これはあまねく物語の型でもある。この行く場所について、斎藤次郎は、
〈単なる空間的な移動ではなくて、目標とするものへの接近、つまり探求にほかならない。〉(『行きて帰りし物語』)
と言っている。では、なぜ行くのか。『文化と両義性』の中で中心と周縁の理論を提唱した山口昌男によれば、日常から出ることで精神を浄化させるため。つまり、どこかに行って帰ってくるが、そのときにはマイナスがプラスに転じている(変化している、気づきがある)というのが、童話を含む物語の原型だ。

『アンガスとあひる』
STORY 犬のアンガスは庭の生け垣の向こうから聞こえてくる声が気になり、生け垣をくぐって向こう側に行く……。
子ども自身が手に取りたくなる内容
ここでは子どもが好みそうな設定を四つに分類してみた。自分が子どもだったときに夢中になった童話と重ね合わせて確認してみよう。
【禁止されていること】
禁忌、禁止は抑圧そのもの。子どもたちは仕方ないとは思いつつ、そうした抑圧から逃れたいと思っている。だから、禁じられたもの、大人がやるなというものをやれたときに、異様と言っていいほどエキサイトする。
【未知の領域】
見知らぬ場所や見知らぬ世界に行き、冒険、探検することにワクワク感を覚える。この未知の世界とは宇宙や異世界とは限らない。「家の外」でも「洞穴」でも、ある年齢の子どもにとっては十分に未知の領域になり得る。
【抱えている問題】
子ども自身が目下抱えているような問題も興味の対象になる。たとえば、「宿題をどうこなすか」「思う存分、ゲームをするには?」「お母さんが口うるさい」「友達とケンカした」といったことも子どもにとっては大きな関心事。
【インナートリップ】
主人公が「行って帰ってくる」ように、読者も物語世界に「行って帰ってくる」。これはある種、旅のようなもの。子どもは主人公と一緒に旅に出て、帰ったときは心がすっきりしている。つらい現実を忘れたい子どもほど没頭する。
02子どもが惹かれる主人公
設定とともに子どもを魅了するのが主人公。では、どんな主人公なら子どもが惹かれ、その童話を読みたいと思うだろう。主人公について探ってみた。
子どもは子どもに共感する
子どもが好きな主人公は子ども。または子どもの心を持った大人。そのことを確認していこう。
【子どもは欠点に反応する】
童話の主人公は、読者対象とイコールであることが多い。小学校低学年向けを想定すれば、主人公は1、2年生になり、中学年を想定すれば3、4年生になる。自分と等身大で、境遇も似ていたほうが共感を得やすいからだ。
ただ、外見は大人でも中身が子どもであれば、大人の主人公も成立する。たとえば、子どもの属性を列挙すれば、「いたずら、わがまま、欲深い、だだをこねる、知りたがり、寂しがり、強情っぱり、粗雑、無知、無神経」など。大人と比べると自制がきかないところがあり、主人公が大人でもこうした一面を主人公の中に見出すと、子どもはそこに反応する。
【自分と似た境遇】
『かいじゅうたちのいるところ』のマックスは狼のぬいぐるみを着て大あばれ。お母さんに怒られても平気で言い返す。いわば悪い子。自分の中にそうしたい気持ちを持つ子は、自由奔放なマックスに惹かれる。

『かいじゅうたちのいるところ』
STORY マックスはお母さんに怒られ、夕飯抜きで寝室に閉じ込められた。その部屋に波が打ち寄せ、船に乗り込み、マックスは魔法を使い、怪獣の王さまになる。
【自分とは違う行動】
現実の子はよい子ほど反抗できない。まして船に乗り込んで怪獣たちのいるところに行き、魔法を使って王さまになることなどできない。だからこそそれを自分の代わりにやってくれる主人公に魅力を感じる。
03山場を作ろう
ストーリーが展開し、大きく盛り上がる山場を作るにはどうしたらいいか、山場が機能するためには何が必要か。こうした構成法について考えていこう。
ストーリーメイクの基本
構成を考えるときには、ざっくりとしたあらすじと主人公の物語上の目的が必要となる。ストーリーメイクをする最低限の基本の手順を知っておこう。
【5W1Hを書き出そう】
ストーリーを考えるには、その前にどんな話かはっきりさせないといけない。「いつ」「どこで」「誰が」「何を」といった設定の部分を書き出しておこう。
【主人公がしたいことは?】
ストーリーにとってもっとも大事なのは、主人公の目的。何をしたいのかだ。主人公は何を望んでいるか、何が欠けているか、最後にどうなりたいかをはっきりさせておこう。
【それをしたらどうなるのか】
主人公には望みがあり、それが実現したらどんないいことがあるのか、逆にどんな不都合なことがあるのか、どうなれば面白くなり、どうなればうまく着地できるかを考えよう。
【まとめてあらすじにしてみよう】
「いつ」「どこで」「誰が」「何を目的に」「何をしようとするのか」「それでどうなるのか」がわかれば、これをそのまままとめればあらすじになる。
山場を作ろう
あらすじが決まったら、山場から考えてみよう。あなたがもっとも書きたい、物語が最高に盛り上がる場面。ここから決めていこう。
【山場とは何か】
山場とはクライマックス。ストーリーが展開し、主人公の目的が叶うかどうか、運命の分かれ目になるような場面。読者の緊張感もマックスになる。
【山場がないと感じたら?】
山場がないという状態には二つあり、それは本当に山場がないときと、山場はあるが機能していないとき。山場がないなら、その前に谷を作り、山場とのギャップを作る。あるいは、山場の前にためを作る。山場はあるが機能していない場合は、山場の前後を再考し、テーマが表現できているか考えよう。
プロットにしてみよう
山場(見せ場)が決まったら、話の配分を考え、プロットに落とし込んでみよう。ここでは短編童話を想定し、起承転結の構成法で考えてみる。
【起承転結の配分は?】
ざっくり言うと、起承転結の配分は、1:4:4:1。起は設定の説明。結は「それでどうなった?」の部分だが、ここは簡潔に。承転が本編とも考えられる。1:4:4:1はあくまでも目安であり、400字詰め原稿用紙5枚なら転を重視し、0.5枚:1.5枚:2.5枚:0.5枚ぐらいを目安に!
【出来事が起きた順に】
大人向けのストーリーと違い、過度に時間軸を崩さない。現在から始まって過去に戻ったり、回想の中でさらに回想するなどすると、子どもは混乱する。多少はかまわないが、基本は時系列で出来事を並べる。わかりにくい伏線なども不要。
【余韻を残す】
出来事は最後まで書いていいが、書かなくてもわかる先のことまでは書かなくてよい。また、最後にテーマをまとめのようにして書くと押しつけがましくなる。テーマについては推測させるようにし、読み手自身に考えてもらうと余韻、余情がでる。
04「で?」を解消しよう
実際に書いてみると、読後に「で?」と思う。「書かれていることはわかるが、だからなんだ?」と思ってしまうのだ。これを解消する方法を考えてみよう。
「で?」と思うパターン
「で?」と思うのは、テーマがよく見えないときや、見えたとしても「だから何?」と思うとき。そうなってしまう原因について考えてみよう。
【話が尻切れ】
昔話「桃太郎」を例にとると、尻切れとは、〈桃から生まれた桃太郎が、三人の家来を連れて、鬼ヶ島に向かいました。終わり。〉というもの。話が完結していないというよりは、まだ設定しか書かれていないので、当然、読み手には「で?」と思われる。
【設定が不十分】
昔話「桃太郎」でいうと、〈桃太郎は鬼ヶ島で鬼退治をし、三人の家来とともに帰ってきました。終わり。〉というもの。起承転結の起承がないから、「桃太郎って誰? イヌ、サル、キジはどんな経緯で家来になったのか」と疑問だらけになってしまう。
【テーマが浮かばない】
〈桃から生まれた桃太郎は三人の家来を連れ、鬼ヶ島で鬼退治をし、財宝を持ち帰りました。終わり。〉は一見問題ないようだが、動機がわからないから、「なんのために鬼ヶ島に行ったのか」と思う。最初に「村を荒らす鬼を征伐する」という目的を明確にしておこう。
「で?」を解消しよう
「で?」と言われてしまうすべての原因はテーマをどう表現したかと、何をテーマにしたかにある。そうなってしまったときの対処法について考えてみよう。
【テーマはなんだったか考える】
書き終わったあと、「で?」と思うときは、テーマがあやふやであることが多い。こういうときは、「で、結局、何を伝えたかったんだっけ?」を考え、それを書き加えるか、書かなくてもわかるようにしよう。
【テーマとして成立しているか考える】
テーマは表現できているのに、それでも「で?」と思ってしまうときは、テーマそのものが凡庸であることが多い。〈悪い子が反省し、今日からはよい子でいようと思う。〉というようなテーマなら、「まあ、それはそうだけど」と思われてしまう。
【もうひとひねりさせてみよう】
「で?」と思ったときは、そこはまだ途中なのだと思い、そこからもうひとひねりさせてみよう。〈悪い子が反省し、今日からはよい子でいようと思う。ところが、次の日から世の中が変わり、悪い子が褒められる世界になっていた。〉と考えれば、「で?」はほんの序盤だったと気づく。