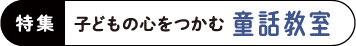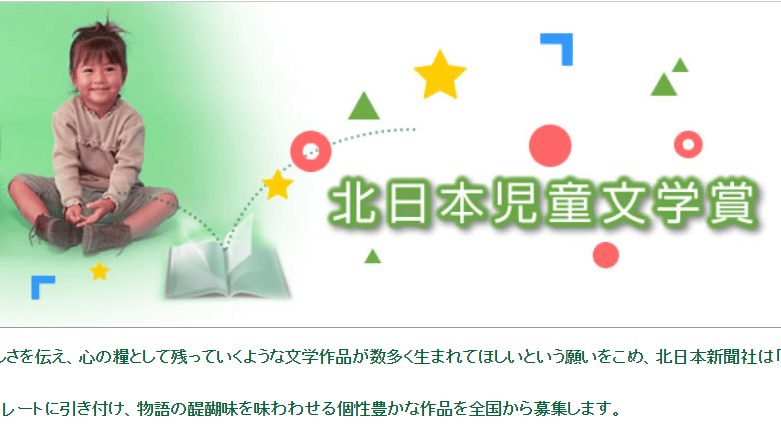#05 7人の受賞者に学ぶ童話のコツ
- タグ


イラスト:seesaw.
過去に童話賞を受賞した7人の方に協力していただき、以下の4項目についてアンケートに回答してもらった。
- ① 子どもが惹かれる設定
- ② 子どもが惹かれる主人公
- ③ 構成法と山場の作り方
- ④ 読後に「で?」と思われず、納得してもらう方法
実力者の言葉に耳を傾け、自分で書くときに生かそう!
01第34回家の光童話賞
平井美里さん
【家の光童話賞】「農業」「自然」などを題材とした童話を募集。読者対象は就学前後の子ども。規定枚数5 枚以内。
- ①設定
- 誰かに読んでもらうという形を想定すると、音読したときに、耳なじみがいいことかなと思います。また言いたくなるような印象的な言葉があることも大事なのかなと思います。
- ②主人公
- 子どもが惹かれる主人公は本当にさまざまに思え、 その共通点をとらえられるならとらえたいと思うものの、いまだつかめず。コツがあるならぜひ知りたいです。
- ③構成法
- どういう結末に持っていくかを先に決めてから、起承転に当たる部分を考えます。枚数をオーバーしてもいったん書ききってみてあとで削ります。短編なら山場と言ってもたくさん枚数を割けないので、あっと思わせる要素を入れる、という意識で書きます。
- ④納得感
- もしも納得いかないときは無理にその流れで話を作って「完成」させず、アイデアをいつかのために貯めておくことにしてはどうかと思います。今の自分には完成させられずとも、のちの自分へのプレゼントということで。
02第11回日本新薬こども文学賞
杉江勇吾さん
【日本新薬こども文学賞】絵本の原作の物語を募集。規定枚数6枚以内。
- ①設定
- 絵本になった私の作品は「みみくそくん」と「はなげせんぱい」。大人から見ると「教育上よくない」「下品」といった感想を持たれるかもしれませんが、子どもには確実に興味を持たれます。
- ②主人公
- 「等身大」または「擬人化」です。特に特徴もない、普通の主人公は設定上強いと思います。あるいは、子どもの大好きな世界に人間(的感覚を持った生物を)を飛び込ませる。鳥になりたいというような感覚です。
- ③構成法
- 構成を考えるうえで、大事にしているのは「題名との距離感」です。ストーリーが進むうちに 、当初のイメージとの距離感を読者が認識し、「思っていたのと違う」という感情にさせる。そのようにして話に引き込む工夫をしています。
- ④納得感
- 自分が聞く側(子ども)に憑依(ひょうい)して、読み聞かせる親を思い浮かべて、自分の中でシミュレーションしてみて、「最後にこれが来たら最高の読後感!」というバーチャル読み聞かせ体験を脳の中でやるしかないと思います。
03第31回新美南吉童話賞
(自由創作部門・一般の部)
のむらきみこさん
【新美南吉童話賞】新美南吉を顕彰した童話賞。規定枚数7枚以内(一般の部)。
- ①設定
- 自分の中の子どもが「うふふ」とか「へえ」とか「ガハハ」とか「悲しい」とか「それから?」と言ったら、興味を惹いたなと思います。この子は「次、もっと違うのが早く読みたい」と言います。
- ②主人公
- 共感できて、スーパーな憧れの主人公かなと思います。「のび太+ドラえもん」や、「アンパンマン+バイキンマン」みたいに、弱さと強さが一緒にある主人公です。
- ③構成法
- 物語を読んだり、映画やドラマを観たりしたあと、ストーリーを起承転結に分けてみたりします。ああ、こんなふうに物語ができているんだなと思います。山場を書くために必要なのは、たぶん素敵な山場のある物語をたくさん見つけて感動することだと思っています。
- ④納得感
- 「で?」と思ってしまった場合、その後を考え、その情景を書きます。その中にまだ気づかなかった何かがある気がします。それでもダメなときは、いつか別の終わりが見つかったり、別のストーリーに組み込まれるときが来るかもしれないので、そのままにしておきます。
04第2回ミツバチの絵本コンクール
ストーリー部門
たじまはるかさん
【ミツバチの絵本コンクール】「ミツバチ」や「はちみつ」をテーマとした絵本のストーリーを募集。10~15場面で、文字数は自由。
- ①設定
- ありそうでなさそうな不思議な世界。不思議なんだけど妙にリアリティーがあって、ちょっとご近所、隣町くらいのところで起こっていそうな感じが、子どもたちを惹きつけるのではないでしょうか。
- ②主人公
- 失敗して、怒られて、でも一生懸命でピュアなヤツ。子どもたちが自分と一緒だと思えて、その失敗にアハハと笑って突っ込めるようなキャラクターが魅力的だと思います。
- ③構成法
- 起承転結を図にしてノートに書き出します。エピソードをそこに付け足して、話の骨格ができたら、配分を決めます。起承転結=2:3:4:1ぐらい。山場は、ピンチがすんなり解決できなかったりなど、窮地に立たせるほうが盛り上がりますので、そこは注意して作っています。
- ④納得感
- いくら考えても「何か違う」という感じから抜け出せなくなったら、いったん考えるのをやめ、できれば数日間、期間をあけてとりあえず忘れます。それから、子どもになったつもりで読み返してみます。全然違う方向からのアプローチが見つかることが多いです。
05第35回
日産 童話と絵本のグランプリ
創作童話部門
水凪紅美子さん
【日産 童話と絵本のグランプリ】創作童話を募集。受賞作は絵本になる。規定枚数5~10枚。
- ①設定
- 思いもかけない不思議なもの、面白いものが出てくるワクワク感のある設定だと思います。それだけでなく、自分にも同じ悩みがある、叶えたい思いがある、という共感が、子どもの心をとらえるのでは?
- ②主人公
- やはり共感できることかなと思います。感情移入ができないとなかなか読み進めてもらえない。また、考え方や行動が“今”じゃないと思われてしまうと寄り添ってもらえない。
- ③構成法
- 起と結は短いほうがいい。承と転はちょっと長めに。山場は都合よく話を進めたいばかりに不自然になることがあるので、一度俯瞰で見るように気をつけます。書いていく過程で山場を作るのは難しいので、山場のアイデアありきで書くことが多いです。
- ④納得感
- あらすじや自分の頭の中だけで考えていると行き詰まるものも、書いてみると打開策が見つかることもある。自分がこの作品で伝えたいことは何か、あるいは、面白いと思ったことは何か、もう一度考え直しつつ書きます。
06第16回ジュニア冒険小説大賞/
第17回北日本児童文学賞
清水温子さん
【ジュニア冒険小説大賞】小学校高学年から楽しめる冒険心にあふれた小説。規定枚数150~200枚。
【北日本児童文学賞】小学校高学年向けまでの児童文学。規定枚数30枚以内。今年、終了となった。
- ①設定
- 現実的でありながら、現実で実際にやると大人に怒られるだろうという設定。
- ②主人公
- 主人公はカンペキじゃない人。他の作品をたくさん読み、自分だったらどういう主人公に設定しただろうと考えていくうちに、自分だけのキャラクターが形になってくる。
- ③構成法
- 山場を先に考える。というか、山場がまっさきに見える。山場の話にどれくらい尺を取るかめどをたて、そこから山場に至るまでの道筋、枚数配分を考えていく。山場を書けば、結はなんとなく目安がつく。
- ④納得感
- 初心に戻る。なぜ、この山場を書きたかったのか、山場が浮かんだときの心のたかぶりを思いだし、迷いを振りはらい、テンションをあげて最後まで書く。落としどころや納得感は、推敲してなんとかする。とにかく完成までつき進む。
07第21回ちゅうでん児童文学賞
眞島めいりさん
【ちゅうでん児童文学賞】小学校高学年から大人までが楽しめる児童文学。規定枚数は40字×30行で50~70枚。
- ①設定
- 子どもをどう描くかもポイントになりますが、同じくらい、大人をどう描くかも大事だと感じます。優しいだけでも厳しいだけでもない、魅力的な大人が登場するとぐっと面白さが増すからです。
- ②主人公
- 作者自身の「この主人公が好き」という気持ちをよりどころにするしかない気がします。まずは書いている自分にヒットしているか、どれだけ思いを込められるかがカギになりそうです。
- ③構成法
- 考えつくかぎりの設定やセリフを書き出し、それぞれが起承転結のどの位置にあると一番しっくりくるか検討しながら全体を組み立てていきます。エピソードの順番を入れ替えるだけでも印象は変化するので、いろいろ動かしてみます。
- ④納得感
- 私もよく「で?」状態になります。「絶対にこの場面が書きたい!」というキーポイントが定まっていないと特にそう感じやすいので、そこをじっくり考えます。