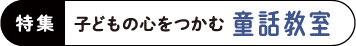#04 プロに聞く わくわくする童話術
- タグ


イラスト:seesaw.
2019年に講談社児童文学新人賞を受賞し、童話・児童文学作家として活躍中の松素めぐりさんに、童話創作のコツについて取材した。



ProfileMatsumoto Meguri
1985年生まれ。東京都生まれ。多摩美術大学美術学部絵画学科卒。2019年、『保健室経由、かねやま本館。』で第60回講談社児童文学新人賞受賞。
01子どもがわくわくする設定
怖さ、未知、そして大人がダメと言うこと
子どもが楽しめる設定について意識されていることはありますか。
松素:自分が子どもの頃に好きだった設定で考えているのですが、現実には起こり得ないことが起きてほしいと思っています。でも、リアリティーは残しておきたい。もしかしたら現実でも起きるかもしれないというわくわく感は残しておきたいんです。
受賞作の『保健室経由、かねやま本館。』がまさにそうですね。
松素:『ナルニア国物語』もそうですが、タンスを開けたら違う世界とか、トンネルがある世界がすごく好きです。「どこでもドア」のようなアイテムがあって違う世界に行くような設定ですね。
未知の世界ですね。子どもってトンネルとか好きです。
松素:うちに遊びにくる子も、なぜか引き出しを開けたがるんですよ。奥が見えないものって、潜在意識的に気になるんだなって思います。
特に男の子ですが、なぜか「うんち」って好きですよね。『うんこドリル』とか、『おしりたんてい』とか。あれ、なぜですかね。
松素:開けちゃダメとか、言っちゃダメかもとか、大人が嫌な顔しそうなことって、楽しいんだろうなと(笑)。
禁忌を破る楽しみってあるんですよね。実際はやれないですが。
松素:やってはいけないんだけど、やってみたらどうなるんだろうというところを、物語の中で体験したい、体験させてあげたいと思いますね。
子育てをされる中で童話創作を始めたとのことですが、お子さんはどんなお話が好きですか。
松素:古田足日さんの『おしいれのぼうけん』が大好きです。閉じ込められるという怖さと、その奥にある世界に行くというところが面白いようで、何回読んでも「もう一回」と言われます。
怖さ、未知。ロングセラーは子どもの心を射る要素を持っていますね。
02子どもが好きな主人公
憎めないあいつ
松素さんはどういう主人公が好まれると思いますか。
松素:私自身のことで言えば、あまりいい子すぎない子を書くことが多いですね。人から見た印象とは違う、心の裏側を書きたいと思っています。明るい子の黒い部分とか、おとなしく見える子の激しい一面とか。そういう裏側の気持ちをすくい取りたいと思っています。
すごく共感できそうな主人公ですが、一方で、嫌な子が反省するのもいかにも教訓的ですし、しかし、嫌な子のままで話を終わらせるわけにも……。
松素:以前書いた作品がまさにそうで、あまりにも裏表がある性格にしてしまったら、私が主人公を、最後まで好きになりきれなくて……。作者が好きになれなかったら魅力的な主人公にはならないと思い、書き直すことに。
どうしたら主人公を好きになれますか。
松素:想像だけで書くのではなく、身近にいる「好きな人」の「困ったところ」を脚色して書けば、どんな主人公でも好きになれるんじゃないかと思います。むかつくやつだけど、こんないいところもあるとか、「憎めないあいつ」って感じになるように意識しています。
主人公の作り方
キャラクター設定について工夫されていることはありますか。
松素:まったく独自のやり方なんですが、私の場合、まずキャスティングするんです。
キャスティング? 映画みたいですね。
松素:実写化された場合、主人公は誰が演じるか、すべての登場人物に配役を当て込むんです。勝手に好きな役者さんをキャスティングしちゃっています(笑)。
モデルがいるので、リアルな人物になりそうですね。
松素:そうなんです。編集者さんにプロットを送るときも、登場人物表に役者さんの写真を貼って、イメージを共有しています。もちろん、作品の中ではモデルがいるとは書きませんが、私の中では完全に人物ができ上がっているんです。
大人を主人公にするときもありますか。
松素:『保健室経由、かねやま本館。』第4巻では、亡くなったおじいちゃんを主人公にしました。
大人を主人公にするときに気をつけていることはありますか。
松素:あまり難しい言葉を使わないようにすることと、大人が思っている気持ちを正直に書こうと意識しました。自分の年齢と違う人間の気持ちを書くので、嘘くさくならないように、主人公が大人でも子どもでも、できる限りその年齢になりきって書こうと思っています。
子どもは敏感だから、嘘だとわかっちゃうんですよね。
松素:そうですよね。なので逆に子ども向けにこう書こうというようなことは意識せずに書くようにしています。
大人の主人公に共感させるにはどうしたらいいですか。
松素:私は特にそうですが、大人だけど中身は子どもというか、子どもと同じ部分が大人にもあると思います。子どもが「なんだ、一緒だ」と思えるように書きたいと思っています。
03映画を作るようにストーリーメイク
山場が書けていないときは前段を見直す
構成はどのようにして作りますか。
松素:私は映画の予告編を見るのが好きで、なんとなくこんな話が書きたいとぼんやり決まったら、頭の中でまず予告編を作るんです(笑)。予告編ですので、キャッチコピーがあり、クライマックスがわかりやすく入っています。クライマックスから考え、そのあと、前後を考えていくというやり方です。
一人で映画を作るような感じですね。
松素:そうです。最初に山場となる場面を考えたら、そのあと、キャスティング。それからプロット作りを始めます。そのとき、最初に既存の曲の中からテーマ曲を決めます。次に、オープニングで流す曲とエンドロールで流す曲を決めて、その曲に合うシーンを考えていきます。
予告編は実際にテーマ曲を聴きながら書くのですか。
松素:ある程度書けたら、曲を聴いて、その曲に合っているシーンになっているか確かめながら書いていきます。
そのあと、プロットを作るわけですが、プロットはどの程度、書きますか。
松素:私の場合はかなり細かく書きます。100枚の作品なら20枚ぐらい。会話も入れられるところはできるだけ入れます。
絵で言うところのラフのような感覚ですね。
松素:そうですね。プロットの言葉をそのまま使って、それを細密にしていく感じです。
山場を書くにあたり、気をつけていることはありますか。
松素:子どもたちに何を感じてもらいたいかを考えながら山場を作るのですが、無理やり感動させようとしているなと自分で思うときがあります。そういうときは、主人公の気持ちがクライマックスに向かってだんだん高まっていくのではなく、そこに至るまでの心情の書き方が粗く、急にたかぶらせてしまっていることが多いように思います。
うまい作品は、クライマックスがいいだけではなく、それまでの出来事を通じていろいろな情報を受け取っていて、この前段があるから泣けるんだというところはありますね。
松素:どうしても筆が止まってしまったら、人の作品を読んで、子どもの心が動くまでの心理描写のうまさを学んで、それからもう一回机に向かうようにしています。
04テーマをどれだけ深掘りするか
テーマに納得感があれば「で?」はなくなる
「で? この話、何が言いたいんだ?」と思われないようにするにはどうすればいいですか。
松素:テーマを掲げるということがとても大事だと思っています。それが伝わる内容になっていないとき、「で?」と思われてしまうような気がします。
テーマが書けていない?
松素:ただ読まされたように思ってしまうのかな、と……。でも、テーマが強く出すぎて、押しつけがましくならないようにも気をつけながら、最後に少しだけ余韻が残るようなあんばいになるのを目指して書いています。
最後にダメ押しのように「だから仲よくしようね」のように書く人がいますが、こういうのは行間に書くものですね。
松素:対象年齢によっても違ってくると思うので、はっきりテーマを示す展開も、もちろん素敵だと思います。昔話のように、最後にわかりやすい教訓があるお話も、個人的には大好きです。ただ、テーマが明確にわかるものより、いろいろな受け取り方ができるもののほうが、自分が書くのには向いていると思っています。
テーマを書いてはいないが、推測はできるようにしておく?
松素:まさにそのとおりで、はっきりとは書かずに想像してもらいたいな、と。答えは一つではないと思うので、その子なりの結論にたどり着けるような投げかけぐらいで終われたらいいなと思っています。
「で?」に戻りますが、そう思ったらもうひとひねりすると、別の観点が見えてくるかもしれませんね。そこから思いもしないテーマを発見するかもしれません。
松素:そうですね。「で?」と思ったらもう一回テーマに立ち返り、テーマはブレていないか、これでいいか考え直すようにしていますね。
確かに、「で?」がでてくる根源は、テーマがよく煮詰められていないことにある気がしますね。貴重なお話、ありがとうございました。