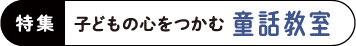#01 『魔女ののろいのアメ』で人気の童話作家・草野あきこさんインタビュー!
- タグ


イラスト:seesaw.
『魔女ののろいアメ』が人気の童話作家・草野あきこさんにインタビュー。童話を書き始めたきっかけや、執筆の際のこだわり、気をつけていることについて聞いた。



Profile2014年、第32回福島正実記念SF童話賞大賞受賞。『おばけ道、ただいま工事中!?』でデビュー。同作品で第49回日本児童文学者協会新人賞を受賞。2019年、『魔女ののろいアメ』が第65回青少年読書感想文全国コンクール課題図書に選出される。
『魔女ののろいアメ』シリーズ
屋台でさまざまなお菓子を売っている、魔女のおばあさん。お菓子には食べた人に悪い効果をもたらす魔法がかけられていて、魔女は町中にお菓子をばらまこうと企む。お菓子を買っていった子どもたちの顛末を、使い魔のカラスに見張らせるが、企みは毎回失敗。挙句に誤って自分でお菓子を食べ、しっぺ返しを食らう。シリーズは『魔女ののろいアメ』『魔女のいじわるラムネ』『魔女のうらないグミ』のほか、おばあさんの子どもの頃を描いた『魔女みならいのキク』も。小学校低学年向け。
01「自分にはこれしかないな」と思って書いていた
童話を書こうと思ったきっかけは何ですか。
草野:小学生のときに先生から日記を褒められたことがあり、もしかして文章を書くのが得意なのかな、という思いはずっとありました。でも本格的に書き始めたのは、結婚して子どもが生まれたあとです。何か新しいことを始めたいなと思って、物語を書いてみることにしました。
子ども向けを選んだのはどうしてですか。
草野:子どもの頃から本を読むのや文章を書くのが好きでした。大人になっても、小さい頃に読んだ物語をいくつも覚えていて、「子どもが読むものって重要だな」と思ったんです。最初は作家になる気もなく、とりあえず挑戦してみようと思い書き始めました。デビューのきっかけとなった福島正実記念SF童話賞に出したときも、何かに引っかかればいいなあくらいでした。
書き始めてすぐに入選されたのですか。
草野:最初はいくつ公募に出しても入選しなかったです。時間の無駄かもと思っていました。だからといってほかに得意なこともなかったので、「自分にはこれしかないな」と思って書いていましたね。7回目か8回目かの応募だった新美南吉童話賞で入賞したときにはじめて、無駄じゃなかったのかもと思い、そこから少しずつ楽しくなってきました。
02書かないことで想像の余白を残す
『魔女ののろいアメ』(草野あきこ 作・ひがしちから 絵・PHP研究所・1200円+税)シリーズの魔女はどうやって生まれたのですか。
草野:アイデア段階では、魔女を出そうとは思っていませんでした。最初は2つの小さなタネだったんです。まずは兄弟の話を書きたいなということ。小さい頃の自分と兄の関係や子どもたちのことを思い出していると、兄弟って普段はケンカするんだけれど、相手が病気になったらずっと心配していたなあという記憶があり、お話にしたいなと思っていました。
もう1つが、イライラしながらお料理をしたときにすごくまずいカレーができてしまった経験ですね。とてもびっくりして心に残っていました。
これらを組み合わせて、お姉ちゃんの悪口を言いながら作ったまずいお菓子を食べさせる話を思いつきました。けれどそれには魔女の力が必要だなと思い、魔女がでてきました。
最初から魔女を出そうとは思っていなかったのですね! では、どのようにして魔女の設定を作っていったのでしょうか。
草野:魔女は、きっと失敗だらけでダメな魔女だろうなと思ったんです。最後には自分が痛い目にあうような。使い魔のカラスも同じように、ダメダメな性格をイメージしています。そのほうが親しみもわきやすいですからね。
そのほかのキャラクターは、性格をなんとなく決めたあとは書きながら「この子だったらどうするだろう」と考えながら進めました。子役俳優さんをイメージすることもありますよ(笑)。「福くんならこう言いそうだな~」とか。
あまり細かく設定を作り込まないのですね。
草野:子どもたちはキャラクターの細部まで知りたいとは思っていないんじゃないかな?と思っています。低学年だと詰め込みすぎると読めないですよね。
さらに魔女に関して言えば、わざと書かないことで親近感を持ってもらえるんじゃないかなと思っています。子どもの頃「かぎばあさん」シリーズを読んだときに、うちにも来るかもと思えたのは、いつ・どこのお話なのか書かれていないからだと思うんです。たとえば、東京都のどこどこで起こったお話としちゃうと、遠い人のように感じてしまうかなと。どこででも起こりえるお話にしたいですね。

「かぎばあさん」シリーズ
『ふしぎなかぎばあさん』(手島悠介 作・岡本颯子 絵・岩崎書店・1300円+税)に始まるシリーズ。鍵っ子(両親が働いているなどして、学校から帰っても家族が家にいないため鍵を持たされている子ども)と、鍵っ子のもとに現れる不思議なおばあさんのお話。
03「子どもの好きなもの」より「私が好きだから」
草野さんはどのように童話を書き進めていらっしゃいますか。
草野:最初は先ほど挙げたような小さなタネをいくつか見つけて、くっつけて短いお話にしてみます。原稿用紙1枚ちょっとくらいの短いものですね。それを元に、話を膨らませながらフローチャートのようなものを書くんです。小説でいうプロットのようなものです。ストーリーの筋が見えたら書き始めて、仮完成させたら推敲します。推敲で大きく書き換えることもありますね。完成までにはだいたい1カ月ぐらいかかります。
子どもに面白いと思ってもらうために気をつけているポイントはありますか。
草野:ウケるようにものすごく意識して書くことはないですね。子どもだからとあなどったり、逆にこびたりしないほうがよいとよく聞きますが、私もそうだなと思います。
私の書くものには魔女や幽霊の出てくることが多いのですが、「子どもはそういうのが好きだから」よりは「私が好きだから」なんですよね。
草野さんが好きなものを書かれているのですね。
草野:はい。そのうえで、子ども向けなので読後感のよさや読みやすさは工夫しています。読みやすさについては、展開を早くすることと説明文を短くすることに気をつけています。
説明は会話として入れることが多いですね。たとえば『魔女のいじわるラムネ』では、魔女の屋台を見つけた男の子が「わあ、緑色のラムネもある」と言うと、魔女が「それは、メロン味だよ」と返すシーンがあるのですが、そんな感じでさりげなく入れることを意識しています。あとは、ストーリーの核心にすぐ入るのも大事ですね。
初心者が童話を書こうとすると説教くさくなったり、子どもにとって面白いのかがわからなくなったりしそうです。
草野:私にもそういう経験があります。公募ガイドの童話添削講座にお話を出したことがあったのですが、後藤みわこ先生がくださった一言が忘れられないんです。
小学校6年生向けにカラスが出てくるお話を提出したら、「小学校6年生が、カラスが主人公の物語を読みたいと思うでしょうか」と返ってきました。私はそんなことも考えていなかったのかと気づきましたね。
人に読んでもらったり公募に出したりすると、自分がどの程度のレベルなのかを知ることができるので、外に出すことが大事だと思います。自分でも客観的に読めるといいですね。
最後に、これから童話を書く人たちへメッセージを!
草野:私も最初は長いものが書けなかったり、盛り上がりしか書けなかったりという感じでした。それでもいいから書くことが大事だと思います。無理やりこじつけてつじつまを合わせようと頑張ると、前のここの場面に伏線を張っとけばいいのかとか気づくんですよね。そうやってよくしていくのがいいと思います。
文章のリズムやストーリーの展開については、好きな作品を自分でパソコンに打ち込んでみて、どんな流れなのかを確認していました。兄弟や子どもがいない方でも、既存の物語や自分の日常から童話を書けると思いますよ。