【原稿チェック完全ガイド】ケアレスミスを減らす校正・推敲テクニックとは?


お悩み④印刷してから、あちこちにケアレスミスを発見します
文章として読まず、記号として見る
校正のひとつのコツは、目的を絞ってやること。「今回は徹底的に誤字を直そう」のようにやることを限定すると見逃しが少なくなくなります。
また、「文章を文章として読まず、1文字ずつ記号として見る」。
「ニ万キロもあった」
上記の「ニ」はカタカナですが、〝読んで〞しまうと誤字に気づきません。「ニ」「万」「キ」「ロ」のように1文字ずつ見ます。
誤字は、誤変換、誤選択、削除し忘れなど本人のミスです。自分で書いた原稿だけに「大丈夫だろう」と思ってしまいがちですが、それではミスに気づけません。人はミスをするものです。
本人は正しいと思っていても、実は誤字ということもあります。「絶対絶命」(正しくは絶体絶命)と書いて、たぶん大丈夫と思わず、辞書で確認しましょう。
また、ゲラ(校正刷り)での校正では、改行一字下げなど書式の不備やノンブル(ページ番号)の間違い、本文、ノンブルの位置などの体裁の不備もチェックします。
読み手のことを考え、読みやすさを追求
最後に編集という観点でのチェックをすることをオススメします。編集的な修正とは、読みやすさの追求です。
改行した際、最後の行が文字で埋まってしまっていると、字面が真っ黒になって圧迫感があります。そこで、行の半分ぐらいのところで改行になるように調整し、誌面的に白い部分を出すようにする。俗に「白を出す」と言いますが、これをやると取っ付きやすい誌面になります。
また、ゲラの段階では、余白と行間(行送り)をチェックしましょう。紙代節約のためにぎっちぎちに文字を詰め込む人もいますが、読み手には苦痛です。
どんな余白、行間がいいかは、同じ判型、同じジャンルの本を探し、読みやすいものに準じれば手っ取り早い。また、極端な当て字、難読文字にはふりがなを振ります。読み手をストレスフリーに!
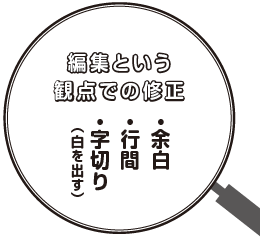
校正で見逃しがちなもの
・似た記号
・似た漢字
・似た熟語
・脱字
・削除し忘れ
・書式の不備
・体裁の不備
・ノンブル
・文字化け
・不統一
一文の推敲チェックポイント
推敲の最後は一文のチェックをします。
たとえば、「欠席したのは」と言い始めて、「風邪をひきました」で結んでいるようなよじれ文を修正します。このような係り受け関係とともに、語順、読点の位置なども確認します。
〈君の家は、まだ僕は行ったことがない。〉
「僕は→行ったことがない」のほうはいいですが、「君の家は→行ったことがない」は「君の家には」がよさそうです。
また、一文は正しくとも、文脈からすると「しかし」はおかしいといったミスもよくあります。前後関係も確認します。
チェックポイント
▶よじれ文
▶接続関係
▶なんとなくすっきりしない
▶語順、読点の位置
▶誤字、記号の書き方
※本記事は2018年1月号に掲載した記事を再掲載したものです。