ふるさと名品オブ・ザ・イヤー
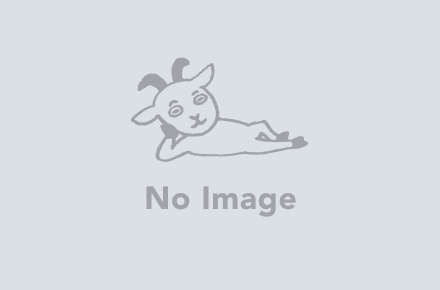
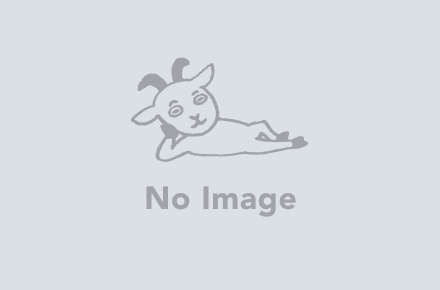
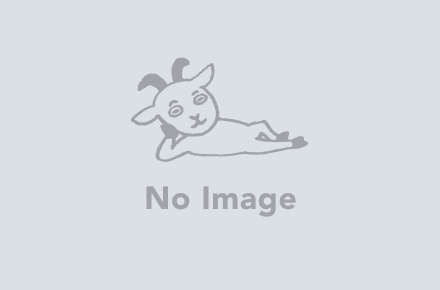
- 締切日
- 2019年1月11日(金)
- 主催者
- ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会
- 賞
- 地方創生大賞、政策奨励大賞、他賞あり
- 応募資格
- 資格不問
「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」実行委員会(実行委員長:古田秘馬、以下「実行委員会」)では、地域の素晴らしさを域外の消費者に直接伝えようとする新たなチャレンジを、より多くの人に知ってもらうことを目的に、表彰制度「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」を今年度も実施いたします。国内の22事業者・団体が集結し、地域の将来を支える名品と、その市場開拓を支援する制度です。地域の魅力づくりを応援する民間企業が、各地域に眠る名品とそれを支えるストーリーや取組を、さまざまな切り口で表彰するのが大きな特徴です。また、内閣府・経済産業省・農林水産省の後援も得て、地域の活性化を生み出していきます。参加企業各社が、知恵と力を合わせて様々な角度から発掘すると同時に、表彰制度を通じてより広く、効果的に発信、周知することを目指していますので、ご応募の程、お願いいたします。 地方創生大賞・地方創生賞とは それぞれの名品や、名品をめぐる人材・取組が、どれだけ地方の変革に向けた機運を醸成し、その実現に成功したかという観点から選考・表彰する賞。「ヒト」「モノ」「コト」の3つのカテゴリごとに地方創生賞を用意し、それぞれのカテゴリの最高位を地方創生大賞とする。 政策奨励大賞・政策奨励賞とは ヒト・モノ・コト、それぞれの見地からの審査では見落とされがちな、政策的見地から意義があると思われる候補を選出。その中から、地方創生を政策的に推進する上で、特に表彰に値すると考えられるものを政策奨励賞とし、その中でも最高位を政策奨励大賞とする。
- 募集内容
- <募集期間>2018年10月1日(月)~2019年1月11日(金) <応募費用>無料 <募集部門> 下記3部門のいずれかから応募ください ヒト部門:地方創生に貢献する人材を対象 モノ部門:地方創生に貢献する名品を対象 コト部門:地方創生に貢献する取組を対象 <評価基準> 【一次審査・二次審査】下記6項目の視点から評価します 1.シンプル / Simple 人物の役割、名品、取組にわかりやすさがあるか 2.ミスマッチ / Miss match 従来と違う考え・アプローチ・手法で取り組み、新しさや思わずを目を止める要素が含まれているか 3.アクション / Action 誰もが欲しい(会いたい)と思うか、成果が出ているか 4.フォトジェニック / Photogenic 写真映えするか、ストーリーがあるか、象徴的な人物がいるか 5.シェア / Share 人と共有したくなる、または教えたくなるか 6.ビジョン / Vision 地域を元気にしているか、または将来性があるか 【最終審査】下記3項目の視点から評価します 1.狙い わかりやすさ、アイデアの新しさ 2.内容 誰もが欲しい(会いたい)と思うか、写真映え、ストーリー性 3.効果 人と共有したくなるか、将来性、地方創生への貢献度
- 作品規定
- <応募方法> ふるさと名品オブ・ザ・イヤーの公式ウェブサイトの専用フォーム: https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-lamikg-50be2fbd70fa5c09dcb4dd7e4b6a32caから応募できます 公式ウェブサイトURL: https://furusatomeihin.jp: %20https:/furusatomeihin.jp <応募条件> 本年12月頃までに、地域の特徴を生かした最近3年を目安に新たに販売・発表された名品を対象と します。ただし、販売・発表から数年経てもまだまだ認知のないコト・モノであれば受賞可能と判断す る予定です。 ▶募集要項: https://furusatomeihin.jp/file/entry/01.pdf
- 応募方法/応募先
- 詳細は主催者WEBサイトを参照
- 応募時の会員登録
- 不要
- 募集期間
- 2018年10月1日(月) ~ 2019年1月11日(金)
- 応募資格
- 資格不問
- 賞
- 地方創生大賞3つ、政策奨励大賞1つに加えて、地方創生賞6つ、政策奨励賞2つと合計12の名品とそれを支えるストーリーや取組を表彰します。 <受賞メリット> 受賞名品は販促機会に受賞ロゴを使用するこが可能になり、日本国内での露出機会や各地のインバウンド対策のツールとして利用されることを想定しています。また、実行委員会に参加する企業が、各事業者の特徴を生かした販促機会が(ECサイト無料掲載など)個別に提供される予定で、政府後援の民間表彰制度の受賞作品として、政府も紹介などを行う予定です。
- 審査員
- 一次審査(1月下旬) 一般公募で個人・団体等から事務局宛に応募頂き、6項目×5点の合計30点で全エントリー名品を公式サポーターにて採点し持ち寄り。合計点のランキングをもとに、二次審査へ進む15候補+αを選定。(ヒト・コト・モノ、各5候補ずつ+α) 二次審査(2月上旬) 6項目×5点の合計30点で全エントリー名品を幹事社で採点し持ち寄り。合計点のランキングと内閣府関係者との協議にて、最終ノミネート12候補を選定。(ヒト・コト・モノ並びに政策奨励賞、各3候補ずつ) 最終審査(2月下旬) 地方創生大賞 地方創生担当大臣を含む有識者・著名人にて最終審査会を実施。3項目×10点の持ち点の投票にて、各部門の地方創生大賞を決定。 政策奨励大賞 左記の審査員にて、各候補関連の書類 最終審査 選考を実施。選考基準は前頁のとおり。
- 補足
- <お問合せ先> ふるさと名品オブ・ザ・イヤー事務局 E-mail:furusatomeihin@jtb.com 営業時間:月~金 9:15-17:45(土日祝休業)
出典:https://furusatomeihin.jp/
コンテストの趣旨がより明確に伝わるよう、公式サイトの画像を一部引用させていただくケースがございます。掲載をご希望でない場合は、お問い合わせフォームよりお申し付けください。