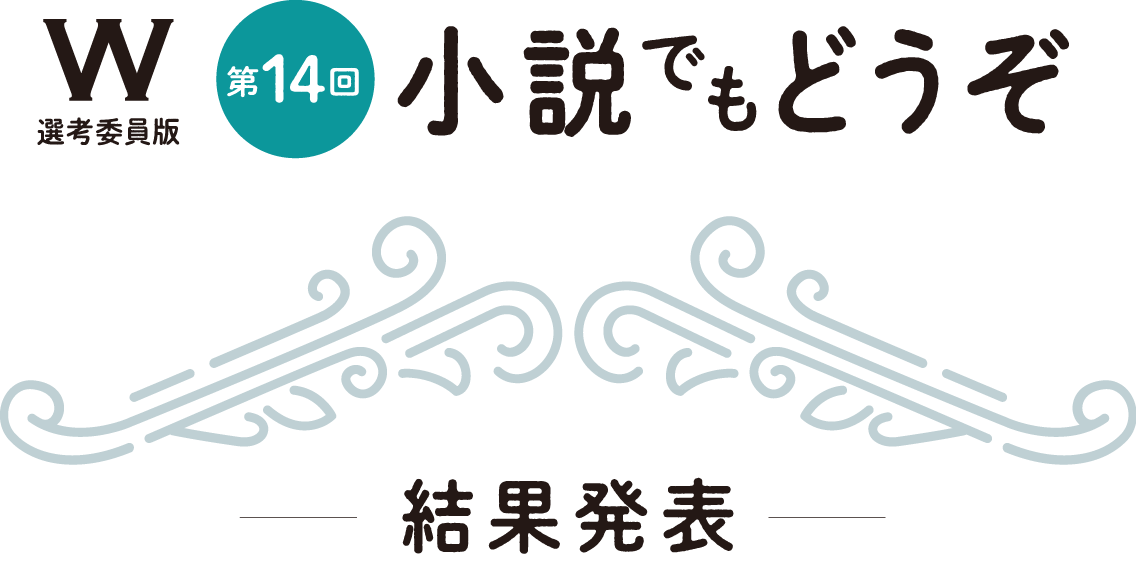第14回W選考委員版「小説でもどうぞ」発表 高橋源一郎&柴崎友香 公開選考会


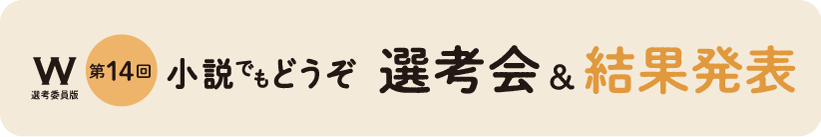

1951年、広島県生まれ。1981年『さようなら、ギャングたち』でデビュー。すばる文学賞、日本ファンタジーノベル大賞、文藝賞などの選考委員を歴任。

1973年大阪府生まれ。2014年、「春の庭」で芥川賞受賞。ほか、『その街の今は』『寝ても覚めても』『百年と一日』『続きと始まり』『帰れない探偵』など著書多数。
オチタイプと余韻が
広がるタイプがある
にしたのはよかった
高橋両親と息子がいて、息子が天に選ばれ、全方位を障壁に囲まれた世界から脱出するというストーリーです。
息子というのは実は熊のぬいぐるみで、舞台はクレーンゲームだったわけですが、卒業祝いとしてパパが娘にぬいぐるみを取ってあげたという話になっています。
いい話ですね。人柄という言い方がありますが、作品柄がいい。△です。
柴崎私も△です。ショートショート的なオチらしいオチですね。前半では障壁に阻まれた世界から息子だけが脱出に成功し、これが卒業なのかなと思うと、そのあとにクレーンゲームをしている人間の親子が登場し、そこにも卒業があります。前半も家族、後半も家族でこれが対比となっていて、よくできた話だと思いました。
柴崎主人公は高校卒業間近。アルバイト先の10歳年上の女性の先輩から夜の公園で卒業祝いにサイダーをもらいます。先輩は高校卒業後、すぐに働き、出産し、DVに遭い、子どもを養うために働いていると聞き、選択肢があることは恵まれていると思うという話です。公園の情景や複雑な人間関係が、短い中に丁寧に書かれていたところはよかったと思います。
ただ、ろくでもない男子学生、この先輩女性からの気づきというのは図式的に配置しすぎかな。オチのような意外性ではなくてもいいですが、「ああ、こういう人なのか」と思わせる感じがあるともっとよかった。△マイナスです。
高橋いい話だけれど、ちょっと弱いかな。もう一押し欲しかった。それぞれのキャラクターが浅めになっていて、表面しか見えていないということがあるのかもしれないし、もう一つエピソードがないと言いたいことがよくわからないですね。
先輩の柴山さんは「昔読んだ本のことを思い出す」と言っていますが、それがわからない。どんな本なのかヒントが欲しい。淡い作品は淡い作品で価値がありますが、淡すぎてしまったという感じですね。△です。
柴崎ごく短い短編はオチがあるタイプと、余韻が広がっていくタイプがあると思うのですが、この作品はオチタイプではないですね。読み終わったあとに残るものを本の話から作ってほしかったですね。
高橋中学一年のあさみには三人のイマジナリーフレンドがいて楽しく過ごしていますが、ある夜、三人が泣いている。亡くなったお父さんの言いつけで大人になるまであさみを見守ってきましたが、今日でお別れだと。それで子ども時代を修了するということで卒業式をし、翌日、あさみには生理が来ます。
よくできた話ですね。けっこう好きです。○です。
柴崎私は△です。前半の卒業式の予行演習は楽しそうで、それが後半の卒業式では泣いていて、対比的になっているところがうまいと思います。
ただ、卒業式でイマジナリーフレンドが言う「素敵な真人間になれますように」や、最後の一文の〈お父さんが見ているような気がして、悪いことは出来ないな〉はあまりにも教育的で、もっと父親の人となりがわかるとよかったと思います。人物が少し型にはまりすぎたかなと思います。
高橋確かに最後の部分は一昔前までの、正しい生き方を伝える童話という感じになってしまいましたね。
書かれた小説は、
印象がよくない
テーマがわからない
柴崎主人公の「俺」が大学に行かないと未来が変わってしまうということで、未来から女性の家庭教師が現れる。信じない「俺」に彼女は、「俺」が愛読しているコミックの36巻を見せる。大学入学後、彼女から36巻が送られてくるが、「俺」は読まずに発刊されるのを待つという話です。
面白く読めました。文章のリズムもいいです。
ただ、ちょっと都合がよすぎるかな。〈俺は柔道二段〉や、〈彼女の指導方法は、時には鉄拳も飛んでくるほどの強烈なもので、ビシビシと教え込まれた〉も、具体的にどういう感じかが見えにくい。△プラスです。
高橋タイトルがいいですね。文章も「ロドリゲスを手に入れろ」というタイトルに合っています。
ただ、突っ込みどころが多くて、今8巻で、全36巻発刊されるまであと28巻ですが、それに百年かかるって美内すずえかよ(笑)。それと漫画のタイトルを作品のタイトルにしていますので、どこかで関係づけてほしかったです。メタ構造にしたらよかったのにという気がします。△です。
高橋「俺」と松田は卒業式には行かず、二人で公園に行きます。周りは大学や専門学校に進学するが、二人とも母子家庭で、将来の夢はなく、働くしかないという環境です。さらに二人とも付き合っていた彼女と別れますが、その理由が「住む世界が違うから」ってどの時代だよって(笑)。昭和だって言わないですよね。で、最後は普通にピンポンダッシュをして、それ以来、松田とは会ってないというんですが、「君はいくつ?」という感じがします。同情の余地はあるにしても、ピンポンダッシュをして終わるのはあまりにも幼い。△マイナスです。
柴崎私も△マイナスです。「母子家庭」「お金がない」「住む世界が違う」など全体にステレオタイプ的な幼い書き方の印象です。それと「俺」と松田が何もかも同じで、松田が他者という感じがしません。もしかすると松田はイマジナリーフレンドかもと思いましたが、松田がいなくなったあと、特に変化したところもなく、この状態ではどう読んだらいいのかなっていう感じがしました。
柴崎舞花は中学卒業から1年しか経っていませんが、もう卒業する。お別れはしたくないが、周りはよかったねと言う。同級生の環奈は夜の繁華街を一緒にうろうろした友達ですが、環奈はまだ卒業できません。実は舞花は、青少年薬物依存回復支援施設を出ていくという話でした。
謎めいた状況や、環奈の腕に蛇が寝床に獲物を引きずり込んだような
ただ、結末が……。△です。
高橋最後の1行で気持ちよく落としてほしかったですね。論理的に落とすとか、技術的に見事に落とすとかいろいろな落とし方がありますが、この作品は一瞬、「なるほど」とは思うものの、あまりいい感じがしない。最後にパッと風景が変わりますが、そのために書かれたという感じがします。オチのために書かれた小説という印象でしたね。
柴崎結末を読んでから舞花の言動を見てみると、ずっと知らないふりをしているように思えるんですよね。あまりひねりのないオチだから、それまでの独特なイメージが道具のようになってしまいます。
高橋やっぱり、オチのためにすべてを使うのはどうかな。△マイナスです。
展開もなかなか見事
最後も気持ちいい
アイロニーを感じる
高橋主人公は還暦でデビューして30年の卒寿アイドル。実際は千寿なのですが、卒寿を機に引退しようと思い、卒寿ツアーをします。しかし、ツアーの最後に倒れ、ようやく寿命が来たという話です。
これもすっきりしない。萩尾望都の『ポーの一族』など長生きした人たちの物語は違う人間観、違う世界観を持っているから独自の魅力になるのですが、この作品の主人公の世界観は普通なんですよね。千年生きて、何も変わっていないように見えるのもどうかと思うので、△マイナスです。
柴崎私は△プラスにしました。人魚の肉を食べたから長生きしたというのは昔からある古典的な型ですが、冒頭の「ババア」呼ばわりが多少の年の差かと思いきや卒寿で、本物のババアもババアやなあというところから面白い。主人公の血を使ってアンチエイジングの薬で大儲けをする人がいたり、今も外見が18歳程度であることも「さすがは女優、自己管理に長けている」と褒められるところには、若く見えることがいいという現代社会に対するアイロニーを感じます。
柴崎怪談探求部の「僕」と先輩は校長室が異次元につながっていることを確かめるため、卒業式の日に校長室に忍び込みます。すると校長室から出られなくなる。実は先輩はこの学校に長年住んでいる幽霊で、「僕」が卒業すると寂しいので閉じ込めたのです。
しかし、「僕」が「卒業してもまた来ます」と言うと、先輩は鍵を開けてくれ、最後に「卒業、おめでとう」と言います。
いい話でした。先輩は実は幽霊であり、卒業するのは先輩ではなく「僕」のほうだったという意外性があります。今日は卒業式で、そのあと校長室にいてと、ちょっとずつ情報を出していく書き方もうまいと思います。先輩と「僕」の関係性もよく、作品には書かれていませんが、「僕」の学校生活が見えるようです。私は〇です。
高橋僕も○なんですよ。最初、誰が卒業するんだろうと思ったのですが、異次元に接続されたところから先輩が幽霊だとわかった。なかなか見事な展開でした。特に最後の「ああ、一つ言い忘れてたな」「卒業、おめでとう」の文章が好きです。この言葉でないといけないし、オチにもなっています。この言葉がここに入るのが正しいというような形で書かれていて、非常に気持ちいい。後輩思いの先輩のキャラもよかったです。